






 缶バッジ
缶バッジ
”ながさき坂道むすめ”
DEPαRTURE x MODAL共同プロデュース「ながさき坂道むすめ」は出島、グラバー園内のミュージアムショップで好評発売中です。
パッケージ表
 パッケージデザイン めず
パッケージデザイン めず
パッケージ裏
 風景イラスト 赤瀬よぐ
風景イラスト 赤瀬よぐ
 浦上~時津エリア キリシタンゆかりの地にある坂道
浦上~時津エリア キリシタンゆかりの地にある坂道
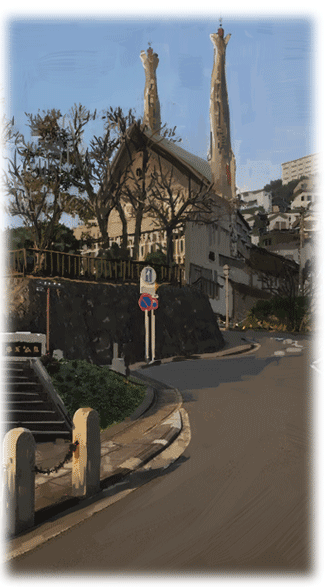
昔は刑場だった二十六聖人殉教の地
NHK横から二十六聖人殉教地へ上る急な坂道。
長崎の中心から見て西側にある坂なので、西坂と呼ばれていた。
昔は海に突き出た小さな岬で、その高台が刑場となった。
秀吉の禁教令により捕らえられたキリシタン宣教師6人と信徒20人がこの場所で十字架にかけられ殉教した。
 |
 |
 |

坂の中ほどから見下ろす。正面右にある白い建物はNHK長崎支局の局舎。その向こうに見える山は稲佐山。

坂の上にある2本の塔を持つ建物は日本二十六聖人記念聖堂で、資料館や記念碑も隣接する。左手の階段を上ると西坂公園に出る。
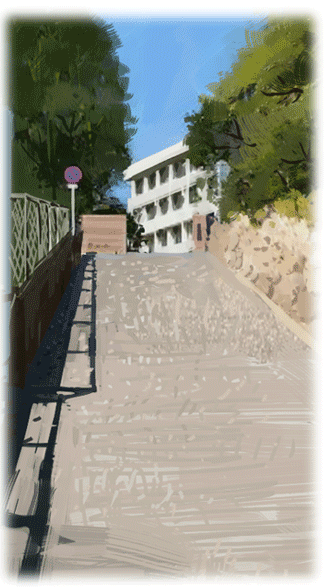
寝坊した高校生にとって試練の坂
竹の久保町の長崎西高等学校正門に至る上り坂。
この坂は学制改革により現在の長崎西高になる前、戦前の旧制長崎県立瓊浦中学校の時代は未舗装であった。
しかし当時からすでにこの坂は「遅刻坂」の愛称で呼ばれており、寝坊して走って登校する生徒たちを苦しめていたという。
 |
 |
 |

正門前から坂を見下ろす。左側には体育館があり、坂の右側は浦上川下流の地域が一望に見渡せる。長崎には高台にある高校が多く、生徒達は汗を流しながら通学している。

爆心地から約800mのこの地にあった瓊浦中学校は原爆により全壊、生き残ったのは60人中わずか数人であった。その他学徒報国隊として出動中の者等を含め、同校の死亡者は405人であったと推定される。

急坂も恐れない長崎のドライバー養成坂
赤迫の六地蔵前から浦上自動車学校方面へと向かう坂道。
この辺りは高台が幹線道路の国道206号線の間近に迫っているために急坂の多い地域で、自動車学校の教習生は路上教習で恐怖を味わっていることだろう。
こうして坂道にはめっぽう強い長崎のドライバーが育成される。
 |
 |
 |

半ば過ぎても坂道は急勾配のまま続く。ここからさらに上ると自動車学校に出る。長崎の自動車学校はこのような坂の上にある場合が多い。

坂の上より見下ろすと山に挟まれた浦上地区の地形がよくわかる。この坂の近くには、変電所の坂に続いて長崎で2番めに急勾配と言われる坂もある。

切通しになる前は牛馬も嫌がる難所
国道206号線、長崎市と時津町の間にある坂。
以前は牛や馬の尻を鞭打たないと登れない程のかなり急な坂だったため、打坂と呼ばれるようになったという。
坂の途中にある地蔵は、昭和22年バスが故障した時に身を挺して乗客の命を救い、殉職した車掌さんをお祀りしたもの。
 |
 |
 |

切通しの崖の高さが、以前峠だったころの道の険しさを物語る。この道はかつて時津街道と呼ばれ、二十六聖人もここを通って西坂へと向かった。
 稲佐~飽の浦エリア 稲佐山から造船所へと向かう、長崎港西側のエリア
稲佐~飽の浦エリア 稲佐山から造船所へと向かう、長崎港西側のエリア
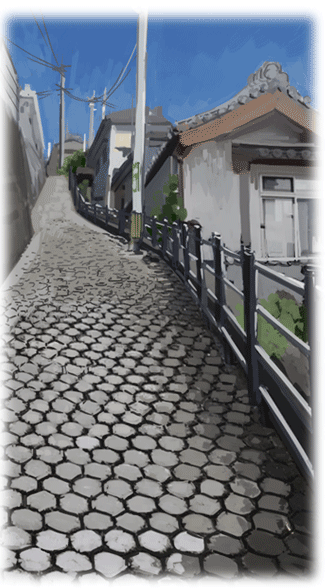
急坂の多い長崎でもNo.1、恐怖の急すぎる坂
飽の浦バス停から変電所に上がる恐ろしく急な坂道は九州電力が建設した私道だが、付近の住人にも利用されている。
最大傾斜角度が20度を超え、車の通れる坂としては長崎でも№1と言われている急坂。
上から見下ろすとジェットコースター並みのスリルを味わうことができる。
 |
 |
 |

坂の途中より見おろした風景。スキーのジャンプ台を思わせる急斜面に目がくらむ。向かいに見える大きなビルは三菱重工業長崎造船所の本館。

坂の頂上にある九州電力飽の浦変電所。車で登ると、車ごとバク転するかと思うほどの急勾配。このような車道の路面には、スリップ防止のための亀の甲型の溝が掘られていることが多い。

長崎市が始めた斜面地整備事業の第1段
飽の浦公園前から上り、入船が丘バス停に至る坂道。
今ある道路を活用しながら車が通る道路へと整備し、斜面地の居住環境と防災性の向上を図るという目的で、坂のまち長崎の地域特性に合わせて長崎市が始めた新規事業「車みち整備事業」の第一弾として完成したばかりである。
 |
 |
 |

舗装されたばかりの真っ白な路面。車も余裕で通れるが急勾配。遠くに長崎港が見える。

さらに下った地域は川の護岸工事をして道幅を広げている。こうして車が通れるようになり、日常生活はもとより救急搬送や消防活動にも利便が図れる。


